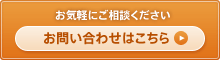地域別最低賃金(H28.10~)を法改正情報にアップしました。
2016年09月30日
地域別最低賃金(H28.10~)を法改正情報にアップしました。
法改正情報はこちら → 法改正情報
文・中嶋倫子
辞令のひながたを様式集にアップしました。
2016年09月26日
ここのところ「勤務地限定正社員」や「勤務形態限定正社員」制度を取り入れる制度設計が多かったのですが、さて、制度が出来上がり、従業員みなさまそれぞれの従業員区分も確定し、、といった段階で、HPの様式集に辞令のひながたをアップしていなかったことに気づきました。
さきほど主な辞令のひながたをアップさせていただきましたので、ご覧くださいませ。
様式集・労務関連様式
今回は以下の3つの辞令のひながたをアップしています。
・従業員区分を改定した時に使用する辞令
・給与を改定した時に使用する辞令
・従業員区分改定と給与改定を同時に発令する辞令
雇入通知書と辞令は、下記のように使い分けてください。
例1) パートタイマー(有期契約)から、正社員(無期契約)への改定 → 雇入通知書
注・パートタイマーとしてはいったん退職し、正社員として採用しなおすという意思表示となります。
例2) 勤務地限定正社員(無期契約)から、転勤ありの正社員(無期契約)への改定 → 辞令
例3) 従業員区分変更は行わず昇給した → 辞令
注・基本的な労働形態が変わらず、処遇が変更される場合。部署変更なども辞令が適切です。
文・西木雅子
コラムをUPしました
2016年09月20日
不動産オーナー様に向けた税務関連コラムをUPしました。
コラムページはこちら→相続財産の組み替えについて
文・横田真紀
9月21日は分水嶺となるか
2016年09月15日
今週、マーケットは9月21日を睨んで不穏な動きとなりました。
9月21日、日銀は金融政策決定会合の結果発表が行われます。
7月29日に黒田総裁が「9月の政策決定会合で異次元緩和やマイナス金利の総括的な検証を行う」と発言して以来、緩和縮小かマイナス金利深堀りかと論議を呼んできました。
8月は長期金利も上昇(債券価格は下落)し、9月2週に入って日経平均も弱含み。
[長期金利グラフと日銀の施策]

同じく9月21日にはFOMCが開かれ、いよいよアメリカが利上げを再開するか否かが発表されます。
今のところ、日銀はマイナス金利を拡大・債券購入方法に調整を加えるのではないかとの見方が優勢、
FRBは利上げ見送りの見方が若干優勢、といったところでしょうか。
マイナス金利が適用されるのは日銀当座預金の一部ですし、現状都銀はマイナス金利部分の資金はゼロ、地銀もほとんどがゼロという状態です。マイナス金利部分の利率を拡大するか、対象とする商品を増やすのか、注目が集まります。
常々申し上げているのは、我々のような長期投資家は、経済に影響を与えそうな大きな出来事の判断は中央銀行の声明を待ちましょう、ということ。
その中央銀行の重要発表が9月21日にはダブルで重なっているわけですから、大注目の1日となるはず。
今週は雌伏の週となったようです。
********
コラムにて、「確定拠出年金 運用のコツ」更新しています。
********
文・西木雅子
コラムをUPしました
2016年09月05日
不動産オーナー様に向けた税務関連コラムをUPしました。
コラムページはこちら → 広大地の評価について
文・ 伊藤友美
社会保険被保険者資格、取得基準の変更
2016年08月31日
平成28年10月1日より実施される社会保険のパートタイマーの適用拡大について
先のスタッフブログ記事にてご紹介させていただきましたが、
平成28年10月1日からは、もうひとつ、小さいけれど重要な改正が発表されていました。
健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準が明確になります。
| 従来の取扱い | 平成28年10月1日以降 |
|---|---|
|
1日または1週の所定労働時間 および |
1週の所定労働時間 および |
「1日」と「おおむね」が外れるだけなのですが、ここは慎重に考えねばなりません。
「おおむね」がついていた効用は、従来の基準から若干外れていたとしても
実態から判断して常用的使用関係にあるかないかを確認すること。
調査などでも「月所定労働日数はだいたい●日ぐらい」のような表現で、特に問題はありませんでした。
改正のタイトルに「明確化」とはっきり書かれていますので、
どこまで明確な基準となるかが重要なポイント。
平成28年8月31日現在、取扱い窓口に確認したところ、
「算出方法を明示していただければ良い」との返答をいただきました。
懐深い指導のようにも聞こえますが、
要は計算根拠を持っておいていつでも説明できるようにしておいてね、ということですね・・・
まずは常時雇用者、一般には正社員と解してよいと考えますが、
この方たちの1週の所定労働時間と1月の所定労働日数を正確に算出するためには、
年間平均をとる必要があります。
様式集に計算シートをアップいたしましたので、ご利用いただければ幸いです。
あわせて様式集の「雇入通知書・期間の定めあり」を、
平成28年10月以降のものに差し替えさせていただきました。
記入要領の注釈を変更しています。こちらもご利用いただければ幸いです。
文・ 西木雅子
平成29年以降の雇用保険改正
2016年08月30日
法改正情報でもご紹介しておりますが、
平成29年から雇用保険制度が一部改正になります。
65歳以上の雇用保険適用拡大
現行法では65歳到達前から雇用され雇用保険に加入していた方は65歳以降も引き続き雇用保険資格を継続することができますが、65歳以上で新規採用された方は雇用保険に加入することができませんでした。
平成29年1月以降は65歳以降で採用された方も雇用保険に加入することになります。
平成29年1月時点で週20時間以上の所定労働時間であり、31日以上継続して勤務する65歳以上の方は、加入手続きが必要になります。
社労士 西木事務所 にて、雇用保険手続きをお任せいただいているお客様には、対象者の方をご連絡させていただきますので、ご本人さまへのご説明をよろしくお願い申し上げます。
なお、雇用保険料には高齢者の免除制度があり、毎年4月1日時点で64歳以上の方は雇用保険資格は継続しますが、保険料は免除となり給与からの控除はありません。
この免除制度は平成32年3月末日まで継続されますので、当面、加入される高齢者の方と事業所のご負担はありません。
給与計算が変わる平成32年4月が近づきましたら、個別にご案内させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
育児・介護休業の改正
平成29年1月から育児・介護休業制度も改正されます。
少々細かい内容です。改正前と改正後を作表しましたので、ご参考までご覧ください。
(会員限定ファイルにて↓)
社労士 西木事務所 に、月次顧問契約をいただいているお客様につきましては、育児・介護休業規程の変更作成をさせていただきます。随時ご案内させていただきますが、該当者発生などお急ぎのことがありましたらご面倒でもお知らせくださいませ。
新たに就業規則・諸規定の作成ご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。
文・西木雅子
社会保険・パートタイマー適用拡大
2016年08月21日
法改正情報コーナーでもご紹介しておりますが、
平成28年10月から短時間労働者の社会保険適用拡大が始まります。
目安として週20時間以上の所定労働時間の短時間労働者が
雇用保険に加えて、健康保険・厚生年金保険にも加入することになります。
ただし、
対象となるのは、社会保険加入者501人以上の事業者だけ。
500人以下の法人・個人事業者は、現段階では適用拡大しなくてOKです。
では、500人以下の企業では、今回の改定は関係のないものとしてスルーしてよいかというと
逆にパートタイマー採用のチャンス到来と見るべきではないかと思います。
今や取り合いの感があるパートタイマーですので、
501人以上の企業でも労働条件を整えて対応するものと推測します。
しかし、
企業にとればコスト増であり採用人数を絞り込むこともあるでしょう。
労働者にとっても、これまでと違う労働条件、社会保険料の発生は負担となり、
契約の継続を断念するケースもあるかもしれません。
500人以下の企業であれば社会保険の負担はないのですから、転職も視野に入ってくるところ。
地元の中小企業にも良い会社があることをアピールする好機到来です。
これまで募集を出してもパートタイマーの応募がこない、とお嘆きだったみなさんは
もう一度パートタイマーの募集をかけてみませんか。
8月末から10月あたり、お試しになる価値はあると思います。
文 : 西木雅子
HPリニューアルしました
2016年08月17日
平素は大変お世話になっております。
この度、私どものHPをリニューアルし、
月次顧問契約をいただいているみなさまだけにご覧いただける
「会員限定」ページを設置させていただくことになりました。
「会員限定」ページにアクセスするために必要なID/Passwordを
昨日8月16日に封書にてご郵送させていただきました。
「法改正情報」コーナーでは、
給与計算に役立つ最低賃金や保険料率等の改訂情報、
労務関連では、平成28年10月からのパートタイマーの社会保険適用拡大について、
「様式集」コーナーでは、
現金出納帳や手形記入帳などの補助簿様式のダウンロード、
雇入通知書や誓約書のダウンロード、
マイナンバー管理様式や派遣元事業主の契約様式などをご提供しております。
今後、随時コンテンツを追加してまいりますので
ご活用いただけましたら誠に幸いです。
また、様式追加や法改正・法解釈追加のご要望など
折に触れてお聞かせいただけましたら誠に幸甚です。
今後ともご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
文 : 西木雅子
[平均賃金の算定]私傷病休業期間がある場合
2016年04月05日
労災の休業補償や会社都合の休業手当、解雇手当や減給のため
平均賃金を計算することがあります。
通常は、算定事由発生日の直前の給与締日から遡って3ヶ月分の賃金総額を
当該期間の暦日で割って、1日分の平均賃金を算出します。
これは1月分まるまる支払われている賃金を3ヶ月分足し、
その期間の暦日で割って1日分を算出する、という感覚、まずこれが原則と理解します。
以下、一般的な例外の認識と処理。
1. 日給や時給などで賃金が支払われ、労働日数が少ない場合
以下の算出金額を最低保障額とする。(労基法第12条第1項第1号)
3ヶ月間の賃金総額 ÷ 当該期間の労働日数 × 60/100
2. 賃金の一部が月給制で支払われ、その他が日給や時給で支払われている場合
以下の算出金額を最低保障額とする。(労基法第12条第1項第2号)
3ヶ月間の日給・時給等の賃金総額 ÷ 当該期間の労働日数 × 60/100
+
3ヶ月間の月給等の賃金総額 ÷ 当該期間の暦日数
これを踏まえて、さらに例外の確認。
3. 算定期間に私傷病による休業期間があり、賃金の減額が行われている場合
以下の算出金額を最低保障額とする。(S30.5.24 基収第1619号)
3ヶ月間の日給・時給等の実際に支払われた賃金総額 ÷ 当該期間の労働日数 × 60/100 (注1)
+
3ヶ月間の月給等の実際に支払われた賃金総額 ÷ 当該期間の暦日数 (注2)
+
3ヶ月間の月給等の休まなければ受け取れたはずの賃金総額 ÷ 当該期間の労働日数 × 60/100 (注3)
以下、月給者の場合の代表的な事例です。
(注1)残業手当などの変動給など
(注2)家族手当・通勤手当など、休業であっても減額されない手当など
(注3)基本給や職能的手当など、休業したことによって減額されている賃金は
休まなければ受け取れたであろう満額の金額についての最低保障額を見る
なお、算定期間内の休業が業務上の事由によるもの、
つまり労災での休業であれば
賃金総額・算定期間の両方から控除します。
いやもう、要注意 (^ ^;
個人的な覚書を兼ねて。