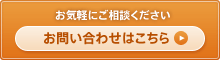メールde給与、始めました!
2016年02月16日
クリニックや国家資格者事務所、個人事務所、飲食業など
様々な業種の、少数精鋭の小規模法人、小規模事業所のみなさまにむけて、
東京FP高松は、新サービス「メールde給与」を開始いたします。
日常業務の邪魔にならない、手間いらずの給与計算業務を実現します。
メールの受送信だけで給与計算が終了!
マイナンバー対応完備!
専用の給与明細用紙不要! 給与封筒は必要部数プレゼント!
詳細ページは こちら をご覧ください。
お見積りは無料です。お気軽にご利用ください。
お見積りご依頼はこちらから!
私どもでは、
昨年秋から既存のお客さまを対象に
マイナンバー導入時の社内体制の構築についてご準備、ご説明をして参りました。
そんな中で、
クリニックや国家資格者事務所、飲食業などの小規模の事業所さまにおいて、
マイナンバー対応への戸惑いや情報不足による不安なお気持ちに触れることが多くありました。
また、法人にもマイナンバーが割り振られることから
社会保険未加入法人・事業所への加入要請が多く見られるようになり
今後さらに給与計算業務が、
多くの事業所さまのご負担となっていくのではないかと考えました。
できるだけ、
手間いらずで、不要な備品にコストをかけることなく、
法令遵守の給与計算のお手伝いをしたい。
そんな思いで、この新サービス「メールde給与」を始めました。
お知り合いへのご紹介、当該ページのリンク、歓迎です。
お見積りは無料。守秘義務厳守。
お気軽にお問い合わせください。
[改正派遣法6]労働安全衛生法第59条のこと
2016年02月08日
毎年6月に提出することになる新・労働者派遣事業報告書。
旧法の特定労働者派遣事業者で、実績ゼロの事業者にも当然に提出義務があります。
本日、当局に
「実績ゼロの場合省略できる項目はどこか、
あるいは、実績ゼロの場合に記載しなければならない項目の指定でも歓迎」とお問い合わせしたところ、
「ただいま検討中につきしばし待たれよ」とのご回答をいただきました。
うーむ。
もしフル回答をせねばならないとしたら、
やはり問題になるのは教育研修の部分です。
私が知る限り、OJT(職場での実地指導)も含めて、
みなさん教育研修はきちんとやられていると理解しておりますが
期限がせまったところでいきなりこの報告書に書けと言われたら、
怒りがこみ上げる方もおられると思います、はい。
そして、
実績有りの事業所ですと、もちろんフル回答なわけでして。
せめて用語説明だけでもと思い、
今回は、年度報告の(4)労働安全衛生法第59条の規定に基づく安全衛生教育について解説します。
安全衛生法59条は、雇入れ時・作業内容変更時の安全・衛生教育について定めたものです。
この項目では、就業前研修・着任研修についての記載を求めているんですね。
注釈をいれつつ、内容についてご紹介いたします。
まずは条文を参照しましょう。
**************************
(安全衛生教育)
第59条
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところ(注1)により、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところ(注2)により、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
****************************
(注1)雇入れ時の教育
原則として以下の事項について教育を行わなければなりません。(労働安全衛生規則第35条)
言うなれば、以下の事項が具体的な研修内容となるわけです。
- 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
- 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
- 作業手順に関すること。
- 作業開始時の点検に関すること。
- 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
- 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
- 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
- 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
(注2)特別教育
特別教育が必要な業務が労働安全衛生規則第36条に定められています。
特別教育は、行政が管理するほどではないけれど、
未研修のまま現場に出してはいけない業務を特定し、
必要な研修を事業者に義務として課しているものです。
有名なところでは「最大荷重1t未満のフォークリフト」があります。
ご存知の方も多いと思いますが
荷重1t以上のフォークリフトは法定の講習を受けなければ運転することはできません。
しかし、1t未満のフォークリフトであれば社内の特別教育だけでOK、となるわけです。
事業報告書の記載要領には
「(4)欄の①欄について、「教育の内容」については、
「4S(整理・整頓・清掃・清潔)運動」、「KY(危険予知)活動」、「ヒヤリハット事例の報告」等
具体的に記載すること。」とあります。
雇入れ時・配置転換時の就業時研修として安衛則第35条の項目を押さえた内容を実施し
「就業時研修」「着任研修」という表記ではなく、
より具体的に研修内容として記載しましょう、ということです。
[改正派遣法5]事業報告の変更
2015年12月17日
特定労働者派遣事業を運営されていたお会社は
これまで6月1日の状況報告、いわゆるロクイチ報告と、
決算確定時の年度報告を所轄労働局に提出されていましたね。
これが法改正により変更となります。
ロクイチ報告と年度報告がひとつになった「労働者派遣事業報告書」を提出することになりました。
提出期限は毎年6月30日です。
書式は厚生労働省HPの様式集内、「労働者派遣事業報告書(様式第11号)」をご確認ください。
いやー、7ページもありますよ(^ ^;
問題なのは、第5面の「キャリアアップ措置の実績」でございまして、
猶予期間中の特定労働者派遣事業のみなさまにもキャリアアップ措置実施の義務が生じますので、
このページが埋められる程度の計画と実績が必要となります。
毎年報告書提出の代行を承っている事業所さまには、年明けご説明とご相談に参りますので
6月に向けてご一緒にがんばりましょう・・・
なお、決算後の報告については、B/S・P/Lの提出と
旧制度でも提出していた「関係派遣先割合報告書」の提出となります。
書式は厚生労働省HPの様式集内、
「労働者派遣事業収支決算書(様式第12号)」と
「関係派遣先派遣割合報告書(様式第12号-2)」をご確認ください。
なお、蛇足ながら、ワタクシの失敗談をひとつ。
改正派遣法の実施が平成27年9月30日ですので
9月末決算・11月末申告の事業所さまから改正法の書式となりまして
つい先日、収支決算書と派遣先派遣割合報告を労働局に持ち込んだんです。
それぞれの報告書冒頭の「許可番号」のところに「特●●-●●●●●●」と書き込んだところ、
「特定は許可じゃないんで、ここに書かないで備考欄に書いてね♡」と指導を受けました orz
はい、もう正式書面上、特定労働者派遣の届出番号を書く欄なんて用意されてないんですね。
潔いですね。
どうぞみなさまお気をつけくださいませ。
なお、香川労働局では、B/SとP/L提出の鑑は様式12号じゃなくて
今迄使ってきた香川様式のアレ、「労働者派遣事業収支決算書(管理用)」推奨のようですよ。
注) ↑というお話で帰ってきたのですが、後日ご担当者からご連絡いただきまして
やっぱり様式12号でいきます、とのこと。香川様式は使わないことになったそうです。
B/S P/L添付の場合には省略できる箇所が多いので、事前に確認されるといいですね。
派遣事業関係の届出は変更が多いので、局のご担当者も試行錯誤されるケースが多いように思います。
だけど、香川のご担当者は丁寧だし親切にしてくださるんですよね。いつも感謝してます。(平成27年12月18日追記)
ご提出前にあわせて窓口にご確認くださいね。
[改正派遣法4]キャリア形成支援制度の計画立案
2015年12月17日
キャリア形成支援制度の計画立案についてのお話です。
前回の記事でもご覧いただきましたが、
キャリア形成支援制度の詳細として公開されている書面がこちら。
社内でキャリア形成支援制度を立案計画する場合の端的な目的は
派遣事業としての許可基準をクリアすることでありましょうから、
時間や必要頻度、コスト負担についての条件、
つまり、要求されている運営形態を理解しておくことは重要です。
箇条書きにすると、以下のようになります。
1. 開催頻度は、1) 入職時は必須、 2) 以後、フルタイムで1年以上雇用継続する見込みがある場合には
年1回必須。
→ 特定労働者派遣から移行する事業所は、原則として年1回必須ということになりますね。
2. 時間は、毎年概ね8時間以上。
3. 教育訓練・研修は、参加する従業員について有給で行い、コストは会社持ちとすること。
次に、内容について。
前提として、「実施する教育訓練が派遣労働者のキャリアアップに資する内容であること」が必要です。
では、キャリアアップに有益であれば、
十年一日のごとく、毎年同じ内容の研修をやり続ければよいかというと
それでは改正派遣法が求めるキャリア形成支援の水準を満たしません。
概念的に申し上げれば、以下の条件を備えていることが必要です。
A. キャリアの節目などの一定期間ごとにキャリアパスに応じた研修等が用意されていること
B. 無期雇用派遣労働者に対して実施する教育訓練は、
長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容のものであること。
ということは、こうした計画をたてるためには
↑の添付ファイル「派遣労働者のキャリア形成支援制度に係る許可基準」の 1 .
「派遣労働者のキャリア形成を念頭においた、
段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定め」る必要があるわけですね。
簡単に言うと
新入社員はいきなり難しいことは無理だから、最初は●●会社に派遣し仕事は●●業務、
何年かたって●●の経験が積めたら、●●の資格をとる、
そしたら▲▲会社に派遣できて、仕事は▲▲業務に変わる、というふうに
ざっくりと仕事の難易度と必要な経験と資格を整理することで充分。
その上で、ホームページやメール一斉送信などの活用や、集合研修の開催、
あるいは外部の研修への参加命令などを決めていかれると良いでしょう。
日本人材派遣協会が平成27年度の厚生労働省委託事業として公表している、
「派遣労働におけるキャリアアップ支援の手引き」がご参考にしていただけると思います。
[改正派遣法3]許可基準要件としてのキャリア形成支援制度
2015年12月15日
さて、前回に引き続き、お題は改正派遣法に則した許可基準確認のお話。
軸としている書面はこちらです。
シート2ページ目、「派遣労働者のキャリア形成支援制度の事項」。
これこそが、今回の改正派遣法の目玉のひとつといえます。
もう少し簡単にまとめたものでは、こちらの資料がご覧いただきやすいかと。
1. の、「派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた
段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定めていること」は、
原則としては特定労働者派遣事業のときのものと変わりません。
追記されている事項を申し上げると、
特定労働者派遣のときの派遣労働者は「無期雇用派遣労働者」になりますので、
この方たちのキャリア形成を念頭に置いた内容とするように指定されています。
特定労働者派遣での派遣労働者は、常勤の正社員を派遣することが原則的な形ですから
この点に関しては、御社の正社員に対するキャリア形成のご方針を書面化することと理解されてよいでしょう。
2. のキャリア・コンサルティングの相談窓口の設置。
これについてはまったくの新規の要件となります。気合いを入れて取り組みましょう。
会社が設置しなければならないものは、
キャリアコンサルティングができる人材と、話し合いができる密室的空間です。
人材面でいうならば、
キャリア・コンサルティングの窓口となる方はキャリアコンサルティングの知見を有していなければなりません。
相応の研修の受講を視野に入れてくださいませ。
一般社団法人 日本人材派遣協会 で、定期的にセミナーを開催しているようです。
空間面でいうならば、
独立した打合せ部屋やパーテーションで区切られプライバシーが保てる空間の設置が必要です。
なお、許可申請チェックシートの1ページ目に
「事業所はおおむね20㎡以上ある」かどうかのチェック項目がありますが、
これは面積だけでなく、キャリアコンサルティングに相応しいスペースの有無も確認項目となるようです。
なお、一般社団法人 日本人材派遣協会 では、派遣元責任者講習も行っています。
特定労働者派遣事業の届出の際受講された方も多いでしょう。
この派遣元責任者講習も、派遣事業更新の度に直近の受講実績が必要ですから、
協会の情報提供は注意してご覧になるとよいと思います。
さて、長くなりましたので、
情報提供の方法や、キャリアアップ措置に関する実施状況の資料作成の注意点について
次の記事でご紹介いたします。
[改正派遣法2]許可申請の基準
2015年12月15日
えーと、[改正派遣法1]から2ヶ月近くが経ってしまいました。
ナニしてたのか、と振り返ってみたのですが、
顧問先さまでの細々とした労務管理の処理が次から次へと発生する不思議な期間でした。
毎週のように退職勧奨の書面や無断欠勤者処理の書類を作ってたなあ・・・
さて、あらためまして、改正派遣法。
今回は事業所の許可基準のお話。
2015年改正派遣法では特定労働者派遣が廃止となり、すべての事業者は派遣の許可を得なければなりません。
ワタクシがもたもたしているうちに、厚生労働省でチェックシートを発表してくれてました(^ ^;
このシートの「質問」をひとつずつ確認していけば良いのです。
が。
チェックのペン先が止まりそうなところをピックアップしてご紹介しておきます。
まずは1ページ目の「財産的基礎」。
原則として、以下の3項目を満たしていることが必要です。
1) 資産の総額から負債の総額を控除した金額(基準資産額)が、
[2,000万円 × 派遣を行う事業所数]以上であること
2) 上記の基準資産額が、負債総額の7分の1以上であること
3) 現預金額が、[1,500万円 × 派遣を行う事業所数]以上であること
1事業所かつ常時派遣する労働者数が10人以下の事業所では特例がありますので、該当する事業所はご確認ください。
さて、この財産的基礎要件、
許可申請の、その瞬間風速でいいの? というご質問をいただきますが、
ご回答は YES です。
ただし、特定労働者派遣事業と違い、改正派遣法の許可申請は一定期間のライセンス制です。
運転免許証と同じで、更新があります。
労働者派遣事業の許可の有効期間は、許可の日から3年。ここで更新手続きが必要です。
更新した場合、次の有効期間は5年。以後、更新を繰り返していくことになります。
更新時には、許可申請時とほぼ同じ内容の提出書類、証明内容が必要です。
つまり、
改正派遣法にのっとって労働者派遣事業の派遣元になろうとする事業者は
少なくとも更新時に添付する決算書では、財産的基礎要件を満たしている必要がある、ということですね。
顧問税理士等にあらかじめご相談され、計画的な財産維持、会計処理を行われることをお勧めいたします。
さて、次の記事では、チェックシート2枚目の「キャリア形成支援」についてご紹介いたします。
[改正派遣法1]特定労働者派遣事業が廃止になりました
2015年10月20日
平成27年9月30日より施行されました労働者派遣法の改正の中で
特に私どものお客様に多く該当する、特定労働者派遣事業の廃止についてまとめていきます。
はい、いきなりですが、
特定労働者派遣事業は廃止になりました。
えええ、この10月もガンガン派遣してまっせ?!と慌てる方もいらっしゃると思いますが
大丈夫、旧制度で届出していた事業所は、
平成30年9月29日までは引き続き特定労働者派遣事業を運営できます。
平成30年9月30日以降も派遣事業を運営したいご希望であれば
改正法にのっとった新制度の番号をとりなおしていただかなければなりません。
そして、この新制度の番号は「許可制」です。
これまでの特定労働者派遣は、「届出制」でした。
書類に不備がなければ、原則として届出を受理してもらえたんですね。
許可を得るということは、それ相応の基準がある、ということ。
ところでこの特定労働者派遣事業ですが、
現在の届出事業所数は56,686、内、派遣実績のある事業所数は27,495、半数に満たないのです。
つまり番号だけはとっているけれど、派遣事業は行っていないよ、という事業所がたくさんあるんですね。
その背景には、旧制度での派遣可能期間は3年だよ、という縛りの影響が色濃いものと思います。
この派遣可能期間、つまりひとりの労働者を派遣できる上限だったり
派遣労働者を受け入れることができる上限だったり、という意味のものですが
もちろん改正法の新制度にも同様のものが設定されています。
これまで無制限だった26業種をもその対象としているところに注意も必要です。
ですが。
新制度では、無期雇用の労働者や60歳以上の労働者を派遣する場合、
この期間制限がかかりません。
つまり、
これまで特定労働者派遣事業として常用労働者を派遣してきた事業所が、
新制度で許可を得て、
これまで通り無期雇用の常用労働者を派遣するのであれば、期間制限なし!
最強! 無双! となるわけなんですが、、、、
許可基準が結構厳しいんです。
次の記事で主要な許可基準を列挙していきますね。
マイナンバー制、ご準備整いました!
2015年08月18日
6月ごろからご訪問時等にお話しておりましたマイナンバー制対応、
大変お待たせいたしました、お客さま向けのご準備が整いました。
来週から書類とデータ一式をひっさげましてご訪問し、
ご説明とお打合せをさせていただきます。
アポイントを順次とらせていただきますので、
お忙しい折りとは存じますが、何卒よろしくお付き合いくださいませ。
ご説明させていただくお客さまは、以下の業務のいずれかをご依頼いただいている方です。
☆ 社労士西木事務所と月次顧問契約をいただいているお客さま
☆ 社労士西木事務所と資格得喪業務、労働保険料確定申告業務、
社会保険定時算定業務の個別のご契約をいただいているお客さま
☆ 東京FP高松または税理士西木事務所と
給与計算業務または年末調整業務のご契約をいただいているお客さま
ご相談対応のみのご契約をいただいているお客さまなど、
私どもが直接に従業員さまがたのマイナンバーをお預かりしないお客さまにおかれましては
大変お手数ではございますが、個別に担当者までご相談くださいませ。
ご契約に応じまして、書類・規程等のひながた、マイナンバーの取扱い方法をご説明させていただきます。

マイナンバーって、回収するだけや〜ん♪と思っている方、多いと思うんですよ。
ところがどっこい、マイナンバーの手強いところは、
回収して、データ管理して、利用して、最後は破棄するところまで、
すべての事業所にべったべたに責任義務が生じるところなんですよね。
そう、我々のような会計労務の事務所だけじゃなく、
従業員がいるすべての事業所に責任義務がべったべたに。
私どもの事務所でも、鍵のかかるキャビネをひとつカラにして管理区域を確保し、
サーバーはセキュリティワイヤーで縛り、
データは最小限の情報を一元管理できるようにしました。ふう。
みなさまにお持ちする書類も、基本方針やら利用通知書やら取扱い規程やら多数、
ええっ、こんなに準備がいるの?!とご機嫌悪くなられる方多いと思うんですよね・・・・
でも大丈夫、私どものお客さまには、社名いれてご担当者名いれて
必要と思われる書類お作りして持っていきますからね、
そのまま掲示して保管してコピーして配ってくださればOKにしてますからね。
そんなわけで、もうすぐ行きます。よろしくお願いします(^ ^
マイナンバー制のこと 〜個人情報の取扱い〜
2015年03月26日
今回は、私たち個人が前情報として知っておきたい
雑学的な情報についてお話していきます。
1. マイナンバーで、すべての情報が筒抜け?!
マイナンバー制について、なんとなく不快感や不安感を覚える、という方も多いようです。
その正体はふたつほどあるのではないかと考えています。
ひとつは、番号で識別されることの不愉快さ。
・・・・これはね、ごもっともなんですけどね、
同姓同名で誕生日が同じ方がいる可能性もゼロじゃないですから
システム的には番号での識別はご容赦いただきたいところでしょう。
もうひとつは、すべての情報が一元管理されるのでは、という不安感。
個人の税金・収入に関する情報、社会保障に関する情報は
当面の間は一括集約されることなく、現行の各行政機関で分散管理される形をとります。

今のところ行政機関から情報がだだモレになったという大事件は起きていないようですから
各機関のセキュリティについては信頼してもよさそうです。
平成27年8月追記・
この記事のアップの後、平成27年6月に年金情報の漏洩事件が起きました。
その後各行政機関はこれまで以上にサイバー攻撃に警戒を強めているようです。
行政機関間での情報のやり取りは行われます。
例えば社会保険の資格取得時、被扶養者になれるご家族の方には収入要件があります。
これまでは所得証明等の添付書類が必要な場合もありましたが
マイナンバー制導入の後は、図解のとおり行政機関間での確認をとることになり
添付書類の省略が可能となります。
もちろん書類作成に際しましては、
私どもではご家族さまのご収入について確認させていただく必要がありまして、
のちのち行政間で確認したら、全然違ったじゃん!! と叱られないためにも
可能な範囲でかな〜り正確な年収のご連絡をいただきたく(^ ^;
何卒よろしくご協力ください。平伏。
2. 個人番号カードは有料?
前回のエントリーで、
多くの方にできるだけ個人番号カード持っていただきたいなー
という主旨のコメントを書きました。
ここで問題は、個人番号カードの発行はいくらかかるの?って話。
ちなみに
マイナンバー制の前身制度といっても過言ではない、
住民基本台帳カードではいくらだったのかというと・・・・
えっ、住基カードって1枚500円もしてたの?!
そりゃ浸透しないわ・・
個人番号カードは無料配布にするようですよ。
お写真撮っていただくのと、手続きのお手間をお願いしますけれど
社会保障・税法上の手続きの簡便化のため、
どうぞふるって個人番号カードをお持ちくださいね♡
マイナンバー制のこと 〜制度導入時〜
2015年03月24日
え? なんスか、マイナンバー制?
と、とぼけていられたのも束の間のこと。
先週、重い腰を上げて研修会に行ってきました。
あらためまして。
平成28年1月から、マイナンバー制が始まります。
先ずは、平成28年1月1日以降に届出する、雇用保険の得喪手続きから使用開始です。
源泉徴収票にもマイナンバー明記となります。
社会保険手続きでの使用は平成29年1月以降。

はい、マイナンバーキャラクター、マイナちゃんです。
ゆるキャラ風ですが、なかなか制度は手強い。
マイナンバーの交付スケジュールは以下のとおりです。
[平成27年10月〜]
住民票のある住所に個人のマイナンバーが記載された「通知カード」が郵送されます。
カードとともに「個人番号カード」の申込書が同封されています。
[平成28年1月〜]
「個人番号カード」の発行を希望される方は、上記の申込書で発行依頼をします。
個人番号カードの交付の際、通知カードを返納します。
そもそもの主旨としては
通知カードは個人番号カードを発行する迄の仮カードという位置づけなんでしょうね。
お会社と我々は従業員お一人お一人とその扶養ご家族の個人番号を入手しなければ
税法・社会保障上の手続きができませんので
先ずは「通知カード」のコピーを回収する必要があります。
制度導入の平成28年1月前であっても、
お会社と我々・事務代行者がデータを回収することは許されています。
ただし、高度に重要な個人情報という位置づけであるため
管理体制はしっかり構築しなければなりません。
このあたり、詳細は個々にご説明に上がりますね。
そして、通知カード情報だけで番号を取り扱ってはならず、
運転免許証かパスポートなど顔写真が添付してある身分証との照合が必要とされています。
なりすまし防止策ですね。
毎日顔合わしてる従業員さんでもか?!とツッコミたくなりますが
法の主旨としてはそういうことです。
ちなみに、平成28年1月以降に申請すると発行される個人番号カードは
顔写真入りですから、こちらの確認であれば個人番号カードだけでOK。
なのでねえ・・・・
個人番号カード発行前の制度開始前・初動段階はしかたないとしても
先々の事務手続きの簡便化を考えましたら、
ぜひ従業員のみなさまと、今後採用される新入社員のみなさまには
個人番号カード持っていただきたいなあ、と思うわけなんですよ。
通知カードだけですと法水準がクリアできませんので
免許証コピーの添付をお願いしなければなりません。

うん、マイナちゃん。
だんだんとキミが面倒くさいキャラに見えてきたぞ(^ ^;
詳細決まり次第ご対応のお願いをご案内させていただきますので
どうぞよろしくお願いします。
続報入りましたら、お知らせしますね。